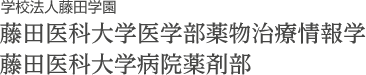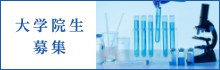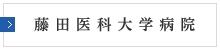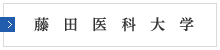お知らせ -
「研究活動のご紹介」についてお知らせを公開しました。
研究に関するホームページ上の情報公開文書
オピオイド誘発性便秘症(OIC : opioid-induced constipation)を有するがん患者に対するエロビキシバット水和物の有効性と安全性に関する単施設後方視的研究
藤田医科大学医学研究倫理審査委員会受付番号:HM18-400
研究責任者:藤田医科大学医学部 臨床薬剤科 教授 山田 成樹
本研究は藤田医科大学の医学研究倫理審査委員会で審査され、学長の許可を得て実施しています。
オピオイドは各種臓器からの消化酵素の分泌を抑え、消化管の蠕動運動も抑えるため、オピオイドを服用されることで、食物の消化が遅れ、食物が大腸で長時間とどまり、水分の吸収は進むため便が固くなることにより、オピオイド誘発性便秘症(OIC : opioid-induced constipation)が起こります。OICは高頻度に起こるため、継続的に下剤を服用していただく必要があります。2018年4月、新規作用機序の慢性便秘症治療薬であるエロビキシバット水和物(商品名:グーフィス®錠)が発売され、臨床において使用可能となりました。一方、グーフィス®錠のOICに対する報告はまだなく、実臨床におけるその有効性や安全性を報告することは有益となります。
対象は藤田医科大学病院において2018年7月から2018年11月までにがん性疼痛に対しオキシコドン徐放錠(商品名:オキシコンチン®錠)を使用した入院患者とし、154名の患者さんの年齢、性別、身長、体重、オキシコンチン®錠1日使用量、レスキュー薬の使用量、グーフィス®錠使用の有無等を調査します。研究期間は、本学医学研究倫理審査委員会承認後から2020年12月31日までとします。
患者さんのデータは安全な管理のもとで保管し使用しますので、登録情報の漏洩がないよう万全な対処をします。また外部への資料・情報の提供はありません。
研究組織:
本学の研究責任者:
藤田医科大学医学部 臨床薬剤科教授:山田 成樹(やまだ しげき)
TEL:0562-93-2208 FAX:0562-93-4537 E-mail:syamada@fujita-hu.ac.jp
本研究の実施に際して、データの利用目的を含む基本情報を本ホームページ上で公開します。もし患者さんがご本人のデータ利用を拒否された場合は、速やかに研究対象から除外いたします。尚、データ利用を拒否された場合につきましても、今後の診療および治療上の不利益を被ることはありません。研究のより詳しい内容をお知りになりたい場合は、他の患者さんの個人情報保護やこの研究の独創性確保に支障がない範囲で、資料を閲覧していただくことが可能です。希望される場合は、担当研究者にお申し出下さい。
何かご意見がございましたら、下記までお問い合わせください。
ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
【問い合わせ先】藤田医科大学病院 薬剤部
部長:山田 成樹(やまだ しげき)
TEL:0562-93-2208 FAX:0562-93-4537
E-mail:syamada@fujita-hu.ac.jp